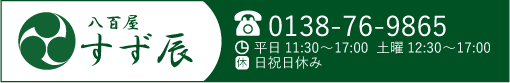旅行途中、札幌にいる中学の同級生の新築の家にお邪魔し、ご家族と一緒に食事しました。
我が家が8・5・3歳、友人のところが7・3歳と似た年頃だったので、子供たちはすぐに意気投合。
食事を挟んで大騒ぎしていました。
そんな中、親同士の会話は教育について…
そこで店主が話題にあげたのが、「保育園義務教育化」。
そのものズバリ、「保育園を義務教育にしてしまおう」という話なのですが、話の元は同名の著作を、社会学者である古市憲寿さんが書き、提唱していることです。
http://dual.nikkei.co.jp/article.aspx?id=5741
まず小学校に上がる前の乳幼児期の教育の大切さを説いていて、そこでの経験で学ぶ力がその後の人生に大きく影響を与えるのです。
その力とは、非認知能力と言われ、学力テストで測ることのできないもので、単純に言うと「生きる力」のようなものです。
例えば、自制心や粘り強さ、物事に取り組む意欲、そして人との関わり方といった「生きる姿勢」ともいえる能力です。
こういった能力は人と関わりから学んでいくため、乳幼児期にできるだけ多くの人と触れ合う環境が大切であり、だったら保育園を義務教育化してしまおうというのです。
一昔前であれば、もっと地域社会が豊かで、社会全体で子供を育てる環境があったのかなぁと思います。
その子供(乳幼児)を育てる環境を保育園に担ってもらおうというのです。
「義務教育」にすれば、「待機児童が…」とか言ってられません。
小学校に通えない子がいないように、誰もが保育園に通えるようにしなければなりません。
3歳までは親が子供を、といった議論もありますが、非認知能力を育てる意味では、母親(父親でもよし)と子供の関係だけよりも、たくさんの人とかかわる時間を取った方が有益です。
我が家の場合、子育ての半分は保育園の先生方に頼ってきましたが、なかなか良い子に育っていると思っています(親ばかでしょうか?)。
どの程度の頻度で保育園に通うかは各家庭の自由にしつつ、保育園という人間社会に子供をほおり込むことが推奨されてもいいのになと思うのです。
みなさんいかがでしょうか。