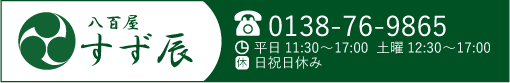(せっかく京都に行ったので、以前書いた京野菜の記事を改題・編集)
『京野菜』。数少ないブランド野菜です。京都の限られた地域で昔から定着
し、種取りされてきた個性的な野菜たち。すず辰(の定番)だと、「賀茂なす」
と「万願寺とうがらし」。京都の料亭で京料理の食材として長年親しまれてきた
もので、とにかくおいしい。賀茂なすは、なすの女王様といった趣で、田楽や揚
げびたしにすると、その肉質のきめ細かさと上品な甘みで思わず口がほころぶお
いしさ。万願寺とうがらしも、とうがらしと言う名とは裏腹に辛みはなく、焼い
たり、炒めたりすると旨みが出て結構はまる方が多い一品。じゃことの炒め物な
んか簡単だけど素敵なおつまみです。
8月のお盆に再訪問した京都の農家さんの共通点は?
太秦の長澤さん「その野菜本来の味が出るように育てるんだよ」、吉祥院の石割
さん「与える肥料によって野菜の味は変わってくる。あと途中の管理でも。だから
、野菜が調理されたときにどういった味になるのか。それをイメージして栽培している。」 これって、どちらも、ただ育てると言うのではなく、食べ物としての野菜
が素材として、どういう味わい・食感・色合いになったらいいかの最終目標をちゃん
と見据えて、種蒔きから、苗の定植、水の管理、追肥等をやっているということ。
これは結構衝撃でした。『姿勢が違う!』と。
野菜が順調に育てばいい、と通常農家さんは考えます。順調にの目安は、苗の
根張りの様子、葉の色加減や、茎の太さ、葉脈の状態などなど、見るポイントは
いろいろ。しかし、どういう味・おいしさになってほしいか考え、そのために今の
野菜の状態を見、必要な手助けを先々を考えて手を打つ。これってかなり高度な
ことです。求める品質が明確であればあるほど、途中の成長過程、栽培手順によ
ってその結果がどう影響するか、アンテナが鋭くなります。さらにすごいのが、
『とらわれない』ってところ。おいしい野菜を作るためなら、手段は問わず、自
らの成功体験も疑って、素直に野菜に向い、その声を聞き、どんどんチャレンジして
いく。常により上を目指し精進されているのです。
まさに「想像力は創造力」です。
「おいしい料理のためのおいしい素材、それを生み出す京都の農家」。その気概
と、料理人との対話の中で、日々おいしい野菜を目指している。これこそ京野菜の
底力ですね。